2022/05/10私の偏光サングラス考
 偏光サングラスが渓流釣りで有効なことは以下の三つです。
偏光サングラスが渓流釣りで有効なことは以下の三つです。(1)水中が見える。(魚の発見、岩、深さの確認よって安全。)
(2)紫外線防止。
(3)目の怪我防止。
今回、レンズは鯖江で作られるコンベックスとタレックスを選ぶことができ、両者の比較をよく聞かれますので、この場でも私的な意見を書きます。
 まず、偏光度や見え方の両者の決定的な差はないと思います。色変化をあまり起こさない方が僕は見やすいと思いますので、一押しはグレー系です。イメージ的にはタレックスのトゥルービューがコンベックスのフィールドグレー。トゥルービュースポーツがフェザーグレー。イーズグリーンがシューターグリンのように捉えてもらっていいです。コート層は若干コンベックスが撥水コートが標準で多いかなというくらいです。アクティブオレンジは可視透過率31%ですが掛けてみるともっと明るく見えます。
まず、偏光度や見え方の両者の決定的な差はないと思います。色変化をあまり起こさない方が僕は見やすいと思いますので、一押しはグレー系です。イメージ的にはタレックスのトゥルービューがコンベックスのフィールドグレー。トゥルービュースポーツがフェザーグレー。イーズグリーンがシューターグリンのように捉えてもらっていいです。コート層は若干コンベックスが撥水コートが標準で多いかなというくらいです。アクティブオレンジは可視透過率31%ですが掛けてみるともっと明るく見えます。
 レンズカラーは好みでいいとして、ハーフミラーか両面マルチコートなのかの差は大きいです。つまりこの違いを考えずにどちらの方が見えやすいという結論するのは早計です。上のブラックフレームのレンズは両面マルチコートです。これは裏表両面に反射防止コートがあるので、背面からも前面からも光が入りやすく、スカスカに見えやすい。ということは、ガラスの中、つまり相手から目が見えます。
レンズカラーは好みでいいとして、ハーフミラーか両面マルチコートなのかの差は大きいです。つまりこの違いを考えずにどちらの方が見えやすいという結論するのは早計です。上のブラックフレームのレンズは両面マルチコートです。これは裏表両面に反射防止コートがあるので、背面からも前面からも光が入りやすく、スカスカに見えやすい。ということは、ガラスの中、つまり相手から目が見えます。
 対してクリアグレーフレームのハーフミラーは前面のコートにミラー加工を施しているため、背面からの光も若干反射してしまい、結果見えにくくなってしまう効果が出ます。数値的には約5%可視透過率が下がると言われています。これはタレックス製を選んでも同じでしょう。良いところは相手から目が見えない。(おしゃれに貢献)ですね。
対してクリアグレーフレームのハーフミラーは前面のコートにミラー加工を施しているため、背面からの光も若干反射してしまい、結果見えにくくなってしまう効果が出ます。数値的には約5%可視透過率が下がると言われています。これはタレックス製を選んでも同じでしょう。良いところは相手から目が見えない。(おしゃれに貢献)ですね。
 クリアオレンジやクリアグレーのフレームは僕も掛けていて明るくて見えやすいと感じます。歳になってきたせいか、常に明るいレンズの方が視力を得やすく、使い心地がいいですね。この点でコンベックスのレンズは色が薄く、明るくて見えやすい。もちろん眩しい時はブラックのフレームやデミブラウンが遮光性が高いのでおすすめですね。ですが渓流ではやはり明るめのレンズに限ります。
クリアオレンジやクリアグレーのフレームは僕も掛けていて明るくて見えやすいと感じます。歳になってきたせいか、常に明るいレンズの方が視力を得やすく、使い心地がいいですね。この点でコンベックスのレンズは色が薄く、明るくて見えやすい。もちろん眩しい時はブラックのフレームやデミブラウンが遮光性が高いのでおすすめですね。ですが渓流ではやはり明るめのレンズに限ります。
 性能の大きな違いを論ずることはできませんが、鯖江で作られるフレームに鯖江で作られるレンズのセットの方が移動距離も少なく同じ町でやり取りするので、価格が安くなっています。また傷にコンベックスは強いと思いました。
タレックスの場合は遠くに持ち込むのでやや施工代金なども高額になる予定です。こう書くとコンベックス推しのように取られるかもしれませんが、僕自身もタレックスも長年使ってきて、大好きなレンズです。初めてイーズグリーンの両面マルチコートを掛けた時の衝撃は忘れられません。
タレックス派を無理に変えようとは思いません。タレックスに拘る人は金額の差異は気にしないくらいタレックス信望が強いでしょうからね。
性能の大きな違いを論ずることはできませんが、鯖江で作られるフレームに鯖江で作られるレンズのセットの方が移動距離も少なく同じ町でやり取りするので、価格が安くなっています。また傷にコンベックスは強いと思いました。
タレックスの場合は遠くに持ち込むのでやや施工代金なども高額になる予定です。こう書くとコンベックス推しのように取られるかもしれませんが、僕自身もタレックスも長年使ってきて、大好きなレンズです。初めてイーズグリーンの両面マルチコートを掛けた時の衝撃は忘れられません。
タレックス派を無理に変えようとは思いません。タレックスに拘る人は金額の差異は気にしないくらいタレックス信望が強いでしょうからね。
 最後に繰り返しますがゲンズブールP3の得意な利点を書きます。
最後に繰り返しますがゲンズブールP3の得意な利点を書きます。(1)レンズが大きくフレームが視界にこないので見えやすい。
(2)顔に沿うようなフレームなので虫、黄砂、埃、背面光をシャットアウト。
(3)圧倒的デザインの良さでお洒落。(普段でもかなりお洒落に使える。)
(4)納期がかかるのが難点・・・2023年2月納品予定→現在受付中です。
 【偏光サングラス・ゲンズブールP3受付はこちら】
【偏光サングラス・ゲンズブールP3受付はこちら】本日の道具
 黄砂飛散の多いこの時期にこのサングラスは必携です。そのほか虫の侵入も防げて、スタイリッシュ。探すとなかなかこんなモードにも決まるデザインは見当たりませんよ。
黄砂飛散の多いこの時期にこのサングラスは必携です。そのほか虫の侵入も防げて、スタイリッシュ。探すとなかなかこんなモードにも決まるデザインは見当たりませんよ。*納期は2023年2月です。



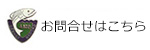









 渓流で遊ばせてもらったら、その地域の地物も楽しむこともおすすめです。思わぬ発見、思わぬ情報を入手することもあります。打算的な僕は以前、わざわざ川が見える食堂に通っては顔を覚えてもらって、国土交通省の数位計だけでは分からない濁りを教えてもらったりしたものです。
渓流で遊ばせてもらったら、その地域の地物も楽しむこともおすすめです。思わぬ発見、思わぬ情報を入手することもあります。打算的な僕は以前、わざわざ川が見える食堂に通っては顔を覚えてもらって、国土交通省の数位計だけでは分からない濁りを教えてもらったりしたものです。

 さて日田は、豆田の町並みでも有名ですが、その川を渡った向こうに美味しいうどん屋があると川で出会った和尚さんが教えてくれました。なんでも裏メニュー的な釜玉うどんがあるらしい。早速、森山さんと行ってきました。乗っているのはチーズにバター。
さて日田は、豆田の町並みでも有名ですが、その川を渡った向こうに美味しいうどん屋があると川で出会った和尚さんが教えてくれました。なんでも裏メニュー的な釜玉うどんがあるらしい。早速、森山さんと行ってきました。乗っているのはチーズにバター。
 うむ、和製カルボナーラか・・・と思いきや、まずは半分だけ麺を食べてくださいと言われて、、、、食べたら持って行かれた、、、、!?
うむ、和製カルボナーラか・・・と思いきや、まずは半分だけ麺を食べてくださいと言われて、、、、食べたら持って行かれた、、、、!?
 すると再び店主が運んできた椀には、肉+明太子+わかめが足されて戻ってきました!!
すると再び店主が運んできた椀には、肉+明太子+わかめが足されて戻ってきました!!
 これは一杯で2種類の味を楽しめる「大超寺スペシャル」という裏メニューらしいです。ペコペコだったお腹がめっちゃ喜んでいます。
豆田の町は渓流の帰りによく子供達を連れて歩いた懐かしい場所です。お土産屋の軒先を通るだけでお祭りに来たようなワクワクした気持ちになりましたね。
これは一杯で2種類の味を楽しめる「大超寺スペシャル」という裏メニューらしいです。ペコペコだったお腹がめっちゃ喜んでいます。
豆田の町は渓流の帰りによく子供達を連れて歩いた懐かしい場所です。お土産屋の軒先を通るだけでお祭りに来たようなワクワクした気持ちになりましたね。
 さて現在、
さて現在、
 ブーツのソールは安全性を決める重要な要素です。サイズも重要ですが、ブーツはサイズに悩んだら小さめよりも大きめを選ぶことをお勧めします。シムスは年代やモデルによって同じ#9、10でもサイズ感が異なるので、ここはスタッフに相談したり、商品説明を熟読いただければ理解が早く進むと思います。
ブーツのソールは安全性を決める重要な要素です。サイズも重要ですが、ブーツはサイズに悩んだら小さめよりも大きめを選ぶことをお勧めします。シムスは年代やモデルによって同じ#9、10でもサイズ感が異なるので、ここはスタッフに相談したり、商品説明を熟読いただければ理解が早く進むと思います。
 「ズバリ、渓流初心者はフェルトにしてください。」
「ズバリ、渓流初心者はフェルトにしてください。」 足の固定はシューレースの紐タイプか着脱容易なボアレースかは全く好みで選んでください。
足の固定はシューレースの紐タイプか着脱容易なボアレースかは全く好みで選んでください。 足首の硬さにうるさい方は時々います。渓流遡行で滝登りやクライミング要素が強い場所を行く方は足首が固定されていない方を好まれます。(体重が少なく、体力のある方向き)ダナゴニアのレザーブーツは柔らかで可動しやすい作りです。反対にシムスは固定タイプが多く里川や歩く距離が長い場合に、疲れた帰り道で足をひねったりする心配がないのが利点です。ちなみに僕は安心安全重視の固定派でシムスブーツが大好きです。でもダナー、カッコいいよね・・・。(実は、、ビブラムを買いました。)
足首の硬さにうるさい方は時々います。渓流遡行で滝登りやクライミング要素が強い場所を行く方は足首が固定されていない方を好まれます。(体重が少なく、体力のある方向き)ダナゴニアのレザーブーツは柔らかで可動しやすい作りです。反対にシムスは固定タイプが多く里川や歩く距離が長い場合に、疲れた帰り道で足をひねったりする心配がないのが利点です。ちなみに僕は安心安全重視の固定派でシムスブーツが大好きです。でもダナー、カッコいいよね・・・。(実は、、ビブラムを買いました。) 渓流釣りを始める方が増えました。意外と身近な自然に、美しく泳ぐ渓流魚が衝撃的。なにより釣道具の美しさにも魅せられる方も多いようです。
僕らとしてはとても嬉しい反響です。(供給が十分間に合っていなくてすみません。)
渓流釣りを始める方が増えました。意外と身近な自然に、美しく泳ぐ渓流魚が衝撃的。なにより釣道具の美しさにも魅せられる方も多いようです。
僕らとしてはとても嬉しい反響です。(供給が十分間に合っていなくてすみません。)
 さて、そんな渓流釣りですが、バスフィッシングやソルトと違って、少しばかり漁協規則や地元へのマナーや暗黙ルールもあります。今回、福岡からほど近い大分県、日田漁協からの要望もあり、せっかく始めてもらった渓流釣りがもっと楽しくなるエッセンスをカスケットからご提案します。
さて、そんな渓流釣りですが、バスフィッシングやソルトと違って、少しばかり漁協規則や地元へのマナーや暗黙ルールもあります。今回、福岡からほど近い大分県、日田漁協からの要望もあり、せっかく始めてもらった渓流釣りがもっと楽しくなるエッセンスをカスケットからご提案します。

 日田漁協に限らず、日本全国の渓流は概ね、漁協が管轄。簡単に言うと無料で釣りをすることはできません。そしてまず、地元の方への印象がよくなることも前提に、見える場所に漁券をつける配慮が欲しいですね。なぜなら山里の渓流には田んぼや川の水を利用してわさびや山菜を生産される方も多く、畦道の踏み荒らしや泥棒(獣かもしれませんが)被害もあり、ピリピリしている方も多いと思った方がいい。漁券がない人は怪しく見えるから、さらに一言「お邪魔致します。」や「ここから入っていいですか?」といった挨拶も重要な渓流釣りのマナーです。話かけると気さくにポイントの情報もくれるし、朝イチに先行者があったよとか教えてくれるのでこれはもうマナーというより情報収集のテクニックなのです。
日田漁協に限らず、日本全国の渓流は概ね、漁協が管轄。簡単に言うと無料で釣りをすることはできません。そしてまず、地元の方への印象がよくなることも前提に、見える場所に漁券をつける配慮が欲しいですね。なぜなら山里の渓流には田んぼや川の水を利用してわさびや山菜を生産される方も多く、畦道の踏み荒らしや泥棒(獣かもしれませんが)被害もあり、ピリピリしている方も多いと思った方がいい。漁券がない人は怪しく見えるから、さらに一言「お邪魔致します。」や「ここから入っていいですか?」といった挨拶も重要な渓流釣りのマナーです。話かけると気さくにポイントの情報もくれるし、朝イチに先行者があったよとか教えてくれるのでこれはもうマナーというより情報収集のテクニックなのです。
 こんな時、少し上流から入っていいだろうと考えるのは絶対にダメです。また後ろから急かすように追い抜きもダメです。大河川の本流釣りは下流に下る場合もありますが、渓流では基本的に上流へ釣り上がります。(ご自身も始めるとそうなるはずですよ。)自然を一人でゆっくりと愉しみたいと来ている方がほとんどです。こんな思いをすると休日も台無し。同じ河川で釣りをするなら、どのくらい離したら良いという規定はありませんが、自分が先行者だったらここまでは離してほしいという範囲はどこまでかを考えて行動してほしいですね。
こんな時、少し上流から入っていいだろうと考えるのは絶対にダメです。また後ろから急かすように追い抜きもダメです。大河川の本流釣りは下流に下る場合もありますが、渓流では基本的に上流へ釣り上がります。(ご自身も始めるとそうなるはずですよ。)自然を一人でゆっくりと愉しみたいと来ている方がほとんどです。こんな思いをすると休日も台無し。同じ河川で釣りをするなら、どのくらい離したら良いという規定はありませんが、自分が先行者だったらここまでは離してほしいという範囲はどこまでかを考えて行動してほしいですね。